【出雲国風土記】日御碕神社(美佐伎社)|「日の本の夜を守る」上下二社の古社|出雲郡・出雲市大社町
『出雲国風土記』に美佐伎社として記される、1300年以上の歴史。
上の宮「神の宮」と下の宮「日沉宮」からなる上下二社を総称して「日御碕神社」。
伊勢が「昼」を、当社が「夜」を守るという神勅譚と、極彩色の社殿・十九社・御神砂など見どころが尽きません。出雲國神仏霊場20社寺の第二十番札所で、教えに因む文字は『守』です。
御祭神
| 主 祭 神 | 天照大御神(下の宮「日沉宮」) / 神素盞嗚尊(上の宮「神の宮」) |
|---|
御由緒(歴史)
日御碕神社は、風土記に美佐伎社と記された古社で、上の宮「神の宮」と下の宮「日沉宮」の二社から成り、両本社を総称して「日御碕神社」と呼ばれます。伊勢が「日の本の昼を守る」のに対し、当社は「日の本の夜を守る」との神勅に基づくと伝えられます。
現在の社殿は徳川家光の命による建立で、西日本では例の少ない総「権現造」。社殿・石造建造物の多くが重文。例大祭は8月7日、夕刻に神幸祭(夕日の祭)が斎行されます。
現地写真ギャラリー
神の宮から見た日沉宮
参道脇にある和布刈神事の図(彫刻...??)
楼門の前にある社号標
楼門をくぐると左右に「門客人神社」。御祭神は櫛磐窗神(櫛磐間戸神)・豐磐窗神(豐磐間戸神)。
蛭兒命を祀る
摂末社と御祭神の名前は向かって右から…(本文の一覧を保持)
※ 日和碕神社 大市姫命
※ 秘臺神社 日神荒魂
※ 曽能若姫神社 曽能若姫命
※ 大山祇神社 大山祇命 磐長姫命
※ 意保美神社 意㳽豆努命
※ 波知神社 須世理姫命
※ 大土神社 大土神
※ 立花神社 伊弉諾尊
※ 中津神社 磐土命 赤土命 底土命
※ 宇賀神社 倉稲魂神
※ 窟神社 稚日女命
※ 眞野神社 近江國諸神
※ 大野神社 出雲國諸神
※ 問神社 稲田姫命 脚摩乳命 手摩乳命
※ 加賀神社 天照大御神
※ 坂戸神社 道返大神
※ 若宮 手力雄命 兒屋命 大玉命
※ 大歳神社 大歳神 奥津彦神 奥津姫神
※ 八幡神社 仲哀天皇 應神天皇 神功皇后
数量限定「砂のお守り」。初穂料500円(赤・青・白)。
経島へ向かう道の途中にある。
出雲國神仏霊場の御朱印
みさきうみねこ街道(県道29号)沿いに駐車スペースがあります。
アクセス・駐車場
島根県出雲市大社町日御碕455。神社そば・バス停付近に駐車場あり。
お問い合わせ
| 所在地 | 島根県出雲市大社町日御碕455 |
|---|---|
| TEL | 0853-54-5261 |
| 駐車場 | 参拝者用駐車場あり/日御碕バス停にもトイレ併設駐車場あり |
| 御朱印 | 有(御守所) |
| 公式 | - |
.JPG)
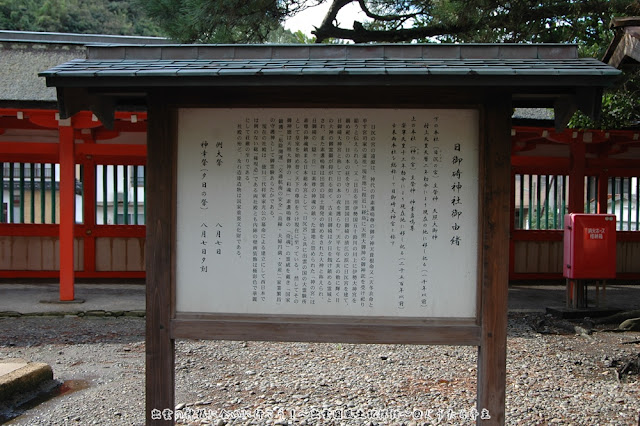

.JPG)
.JPG)





.JPG)





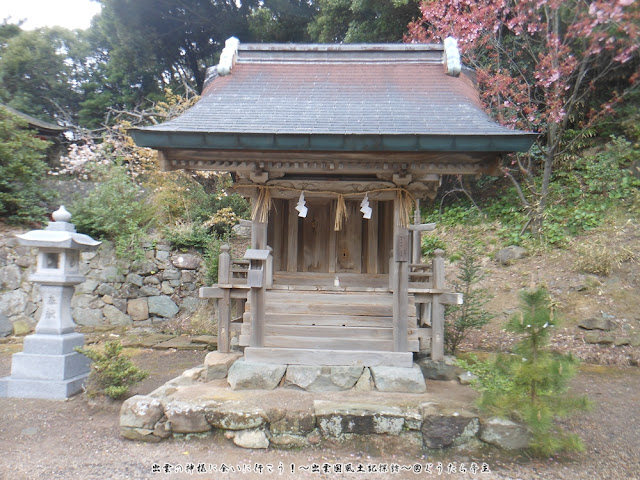

.JPG)





.JPG)












0 件のコメント:
コメントを投稿